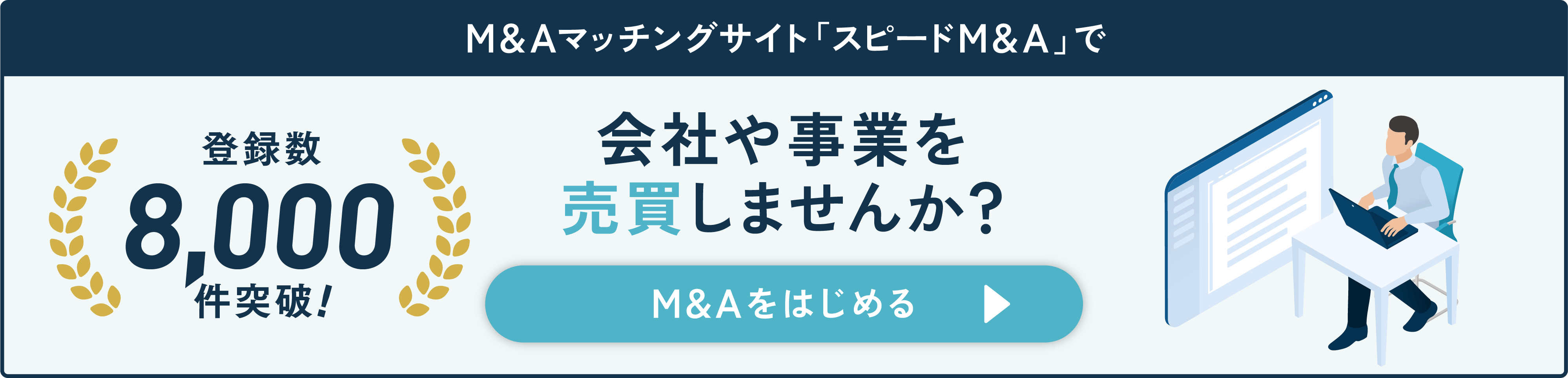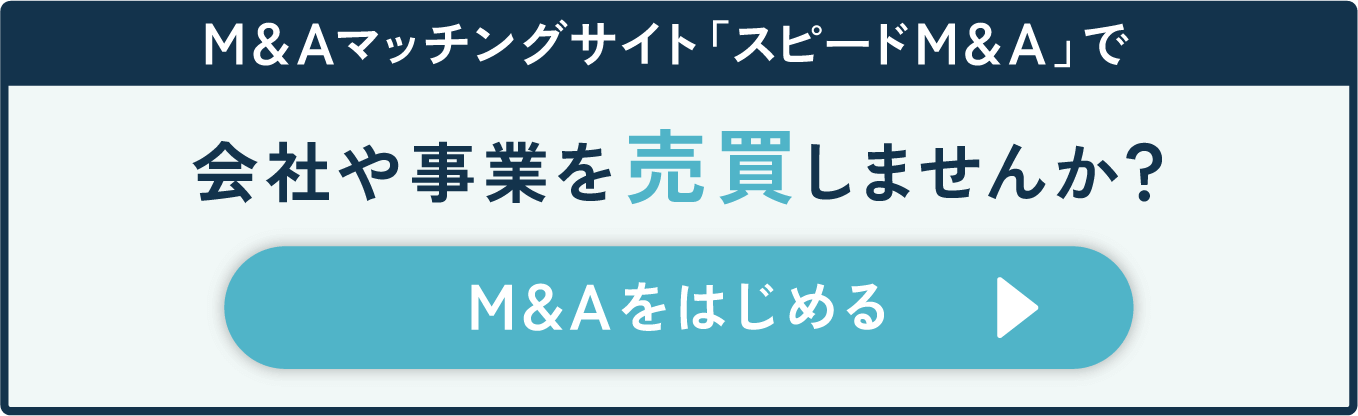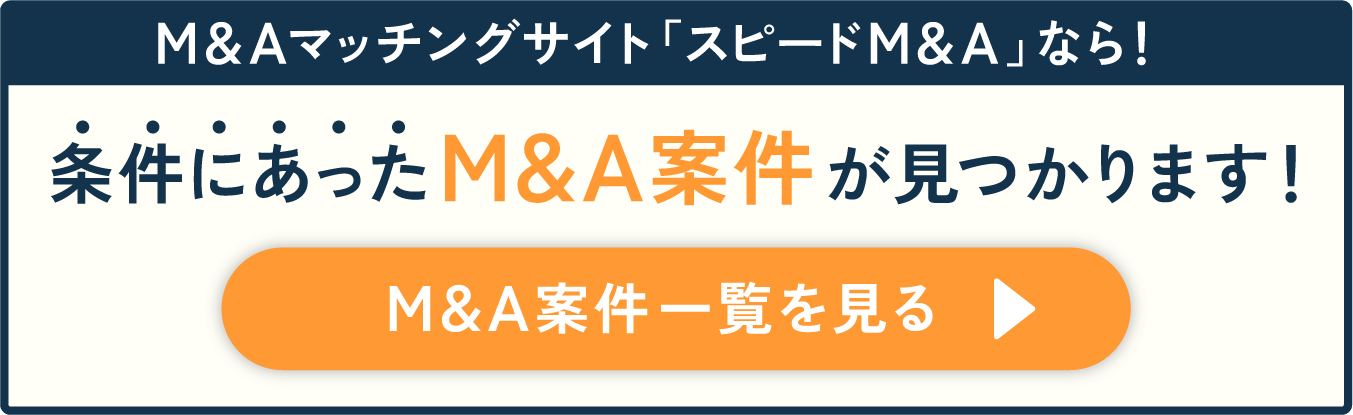会社売却や買収を考えている場合、DCF法という言葉を聞くことがあるかもしれません。
DCF法は難しい計算方法のように思われている方が多いかもしれませんが、一度原理を理解してしまうと簡単に感じられるはずです。
今回はDCF法について複数の図解を入れながら具体的にわかりやすく解説していきます。
DCF法とは
DCF法とは、Discounted Cash Flowの略で、将来獲得できるキャッシュフローを割引現在価値になおすことで株式や不動産、事業の価値を算出する方法です。
M&Aをはじめとして、ビジネスや金融の世界で広く使われています。
DCF法のイメージ
DCF法は「現在価値」と「将来価値」の違いを理解するとイメージしやすくなります。
現在10万円持っており、年間10%の利回りで運用できたとすると、1年後の価値は11万円となります。
この時、年間利回り10%で運用できることを前提にすると、現在の10万円と将来の11万円は、等価となります。
将来の11万円から現在の10万円になおすことを、割引計算すると言い、これがDCF法の基本となります。
DCF法が利用される場面
DCF法が利用される場面は下記のように数多くあります。
- ある会社を買収する際、妥当な買収金額を算定する場合
- 自分が経営する会社を第三者へ売却したいが、適正な金額がわからない場合
- 友人の会社にマイナー出資を行う際
- 不動産価格が割高か割安かを判断したい場合
- 新規事業に投資するべきか投資しないべきかの判断を行う場合
上記はあくまでも事例であり、DCF法ではなく違う算定手法を用いることもあります。
案件の規模や状況、売り手と買い手の交渉バランスなどから、実務にて使われる方法が決まってきます。
DCF法は、最も理論的な方法であると言われており、専門家に株価算定や事業の価値算定を依頼すると、ほとんどのケースでDCF法が採用されています。
工場の建設費用は今払いますが、利益(キャッシュフロー)が出る期間は数十年間にも及ぶことでしょう。
この場合、DCF法により事業価値がゼロ以上であれば投資する、マイナスであれば投資しないといった判断基準とするケースがあります。
DCF法による価値算定プロセス
DCF法の基本的な概念をおさえた後は、実際にDCF法を使って簡単な価値算定を行ってみましょう。
株式会社A社を例にとって、5ステップでA社の価値算定をDCF法により算定していきます。
1 将来フリーキャッシュフローの算定
最初のステップは、A社が将来どれだけキャッシュフローを稼ぐかを見積もる必要があります。
損益計算書における利益の金額でない点には注意してください。
DCF法において使用されるキャッシュフローはフリーキャッシュフロー(FCF)と呼ばれるものです。
フリーキャッシュフローとは、事業で稼ぎ出したキャッシュフローから事業継続に必要な支出を差し引いて計算されます。
フリーキャッシュフローは、下記の2通りの計算式で計算することができます。
- 営業キャッシュフロー ー 投資キャッシュフロー
- 営業利益 × (1ー税率) + 減価償却費 ー 投資 ± 運転資本
①はキャッシュフロー計算書から、②は貸借対照表と損益計算書から計算できます。
ここでは、A社の将来フリーキャッシュフローは、5年間で下記のとおり成長していくと算定します。
| 1年後 → | 1億円 |
| 2年後 → | 2億円 |
| 3年後 → | 3億円 |
| 4年後 → | 4億円 |
| 5年後 → | 5億円 |
2 割引率の算定
DCF法は将来得られるキャッシュフローを割引現在価値になおすための割引率が必要です。
DCF法で用いられる割引率は「加重平均資本コスト」と呼ばれるものを使います。
加重平均資本コストとは、
- 借入で調達したことにより債権者から求められるコスト
- 資本で調達したことにより投資家から求められるコスト
を加重平均したものです。
①借入で調達したことにより債権者から求められるコストは、借入金の金利が該当します。
②資本で調達したことにより投資家から求められるコストは、一見するとゼロで良いように思われるかもしれませんが、
株主は見返りがなければ投資をするはずはありません。
株式会社は、配当金の支払や株の値上がり益で、株主の期待に答えなければならないため、
株主から要求される期待収益率(利回り)がコストとなります。
A社の借入金3億円(金利2%)、資本金7億円(株主から要求される利回り12%)とした時の加重平均資本コストは下記のとおりです。
2%×3億円/10億円 + 12% × 7億円/10億円 = 9%
3 残存価値の算定
将来フリーキャッシュフローと割引率を算定した次は、残存価値を算定します。
残存価値(ターミナルバリュー)とは、将来キャッシュフローを見積もった期間後の価値を計算したものです。
処分価格とも言われており、たとえばパソコンを20万円で購入した際、5年後の残存価値=処分価格は2万円程度でしょう。
パソコンなど「物」であれば残存価値は簡単に見積もることはできますが、会社の残存価値はどのように計算するべきでしょうか。
会社は未来永劫存続すると仮定されて財務諸表も作成されています。
そのため、残存価値も会社が永遠に存続しキャッシュフローを生み続けると仮定して計算します。
A社は5年後に5億円のフリーキャッシュフローを獲得しますが、6年後以降も5億円が永久に継続するとしましょう。
残存価値は下記の計算式で計算することが出来ます。
5億円 ÷ 割引率(加重平均資本コスト)9% = 55億円(小数点以下切り捨て)
なお、6年後以降、毎年1%ずつ永久に成長するケースでは、下記の計算式となります。
5億円 ÷ (割引率9% ー 成長率1%) = 62億円(小数点以下切り捨て)
なぜこのような計算式になるのでしょうか?
無限にキャッシュフローが得られる際の価値算定の計算式は永久還元法と呼ばれ、数学的に証明されています。
数式の証明はここでは省略していますが、税法などでも認められている方法です。
4 割引現在価値の算定
将来フリーキャッシュフロー、割引率、残存価値を計算した後に、最後に割引現在価値を算定します。
下記の図のとおり、割引現在価値は46億円(小数点以下切り捨て)となります。
5 事業価値と株主価値の違い
DCF法により計算してきたのは「事業価値」です。
事業から生み出す将来キャッシュフローを元に計算しているため、事業そのものの価値しか反映されていません。
A社の株主価値を算定したい場合は、ここから非事業用資産(有価証券、土地、事業に必要のない現預金等)を加算し、有利子負債を減算します。
A社は総資産10億円のうち2億円が上場有価証券、負債3億円はすべて有利子負債とします。
この時のA社の株主価値は下記のとおりです。
A社の株主価値:事業価値46億円 + 2億円 - 3億円 =45億円
A社の発行済み株式数が1万株だとすると、A社の一株あたり株価は45万円(45億円÷1万株)と計算できます。
また、「事業価値」に「非事業用資産」を加算した価値は「企業価値」となります。
事業価値、企業価値、株主価値の関係図は下記のとおりです。
DCF法の留意点
以上のように、DCF法の基礎的な部分を解説してきました。
ここからは少し細かい論点も含めて、DCF法の留意点を解説していきます。
1 DCF法のメリット・デメリット
DCF法は事業価値を算定するうえで便利な方法ですが、完全な方法ではありません。
下記のとおりメリット・デメリットがあります。
- DCF法のメリット
- 過去ではなく将来のキャッシュフローを元に計算されているため、事業計画を反映しやすい
- 最も理論的な方法と言われており、大企業も使用している
- DCF法のデメリット
- 将来キャッシュフローや割引率の見積もりを誤ると、算定結果が大きく変動する
- いつでも使えるわけではない
2 DCF法が使えないケース
DCF法のデメリットの1つとして、「いつでも使えるわけではない」ことが挙げられました。
DCF法が使えないケースとは下記のとおりです。
企業が清算する際DCF法は、企業が永続的に存続することを前提に残存価値を計算してきました。
企業が清算する場合、これ以上の将来キャッシュフローも生み出さないため、割引計算をすることができません。
企業が清算する際の株価算定は、DCF法ではなく、「修正簿価純資産法」など貸借対照表のみに注目した計算方法を適用する必要があります。
相続税評価未上場株式を相続する際、未上場株式の株価算定を行う必要があります。ここで、税法上、DCF法は相続の場合には適用することができません。
DCF法は見積もり要素が多く入っており、税法のように決まりきったルールを作ることができないためです。
相続の際の株価算定は、配当還元方式、純資産価額方式、類似業種比準価額方式の3つの計算方法しか認められていません。
3 割引率の詳細な計算方法
「 割引率の算定」では、株主から要求される利回りを12%と仮定して計算しました。
株主資本コストの理論的な計算方法の一つである「CAPM理論」を解説します。
CAPM理論とは、Capital Asset Pricing Modelの略で、数理ファイナンスにおけるモデルであり、リスク資産の均衡市場価格に関する理論です。
具体的には、株主資本コストは下記の計算式で表現することができます。
株主の期待利回り =
①リスクをほぼ追わずに獲得できる利回り +
②対象企業に投資するリスクを追う代わりに追加的に求められる利回り
①は、長期国債の利回りを使います。
実務的には10年国債利回りを使うことが多く、2020年7月時点だと0.02%程度です。
②は、エクイティリスクプレミアム(株式市場に求められる超過利回り)×ベータ値( 対象企業のリスクと株式市場全体のリスクを表す相関係数)により算出されます。
以上より、株主の期待利回りは、
リスクフリーレート + エクイティリスクプレミアム × ベータ値
と計算されます。
エクイティリスクプレミアムは、仮に株式市場全体に対して投資する場合の利回りです。
東証TOPIXの利回りと日本国債利回りとの差などを分析して、実務上は5%~10%程度を使うケースが多いです。
ベータ値は、株式市場全体の変動に対して、対象企業の利回りがどれだけ変動するかを表す指標です。
たとえば、TOPIXが2%動いた時に、対象企業の株価が3%動いた時のベータ地は1.5です。
対象会社が未上場企業である場合は、類似の上場企業のベータ値を使って計算します。
また、評価対象企業はCAPM理論には含まれていない固有のリスクがある場合は、それを考慮して割引率を算定します。
以上より、リスクフリーレート0.02%、エクイティリスクプレミアム8%、ベータ値1.2、固有のリスクプレミアム3%としたときのA社の割引率は下記のように計算されます。
0.02% + (8% × 1.2) + 3% = 12.62%
ベンチャー企業や極めてリスクが高いと認められる場合は、30%といった高い割引率を採用する場合もあります。
4 非流動性ディスカウントとの関係
DCF法により株式価値を算出した後に、さらに非流動性ディスカウントで割り引くという考え方があります。
非流動性ディスカウントとは、評価対象会社が未上場企業であれば、上場企業のようにいつでも売買できるわけでないので、その分評価額を減額するべきであるという考え方です。
たとえば、A社の株主価値は45億円と算出しましたが、未上場企業であるため、非流動性ディスカウントを20%とし、
A社の株主価値は45億円×(1-20%)= 36億円とすべきである、ということです。
この考え方は、2015年3月26日に最高裁判所によって、明確に否定されました。
理由としてDCF法には、市場における取引価格の比較という要素が含まれていないため、とされています。
企業価値評価の手法として、DCF法と並んで使われる方法として、類似会社比準方式(マルチプル)があります。
類似会社比準方式は上場株式の評価倍率を使って計算しているため、類似会社比準方式であれば、非流動性ディスカウントを用いるのは妥当ということのようです。
DCF法を学び始めたり、実務で使用しだしたりすると、たまに非流動性ディスカウントについて混乱してしまう場合があるので、注意しておきましょう。
DCF法の実務への活かし方
最後にDCF法がどのように実務へ活かされているか、具体例を交えながら解説していきます。
バリュエーションレポートが必要なケース
下記のようなケースでは、バリュエーションレポート(株価算定書)の作成を会計事務所などの外部専門家へ依頼するケースがあります。
(1)TOBを行う場合
上場会社に対してTOB(株式公開買付)を行う際、買い手はいくらの価格で株式を買うのかを公開します。
対象企業では、株主に対してTOBへの応募を促す場合があります。
その際、TOB価格の妥当性を考えるための材料として、バリュエーションレポートを取得することがあります。
2020年2月4日、オーデリック社は「TOBによるMBO実施と応募の推奨」というリリースを出しています。
この中で、山田コンサルティンググループから株式価値算定書を得ている旨の記載があり、マルチプル法とDCF法により企業価値を算出していることがわかります。
【参考】MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ|オーデリック社
(2)未上場企業を買収する場合
未上場企業を買収する場合、上場企業と異なり市場価格はありません。
そのため、上場企業が未上場企業を買収する際は、買収価格の参考にするためにバリュエーションレポートを取得することがあります。
バリュエーションレポートには、株価はひとつの数字として報告されるのではなく、レンジで報告されることが通常です。
たとえば、DCF法により算定したA社の株価は一株35万円~50万円のようなイメージです。
結果として、バリュエーションレポートのレンジ内に買収価格が収まっていれば、買収価格が妥当であることを説明することが可能となります。
(3)自分が経営している会社を売却する場合
買い手だけでなく、売り手が自らバリュエーションレポートを取得することがあります。
バリュエーションレポートを得ることで、著しく安い価格で株式を売却してしまうリスクを減らすことができます。
買い手としては、売り手の意思が大きく反映したバリュエーションレポートと考えるため、完全に信じることはできませんが、参考にすることはあります。
買い手がバリュエーションレポートを依頼する場合、財務税務デューデリジェンスと同時に依頼するケースが一般的です。
M&Aでの利用事例
以上のように、バリュエーションレポートを取得することについて説明してきましたが、すべてのM&Aにおいて外部専門家が作成するものが必要なわけではありません。
とくに中小企業のM&Aでは、取引金額が自分の意思決定において重要でない場合、リスクが低いと見込まれている場合、などは取得しないケースが大半です。
もちろん、中小企業のM&AでもDCF法についての知識を深めておいて損はありません。
- 買収案件が割高なのか割安なのか、簡易的な評価を自らができるようになる
- 自社を売却する際に、割安な価格で手放してしまうことを防げる
-
専門家とDCF法や企業評価について、専門用語を使われても付いていくことができる
仮に理解するのが難しかったとしてもM&A自体を諦める必要はありません。
気になっている買収案件や自社を売却したい場合、気軽にM&A専門家に相談することができます。
スピードM&Aには、M&Aに詳しい専門家が多数在籍しておりますので、お気軽にお問い合わせ頂けましたら幸いです。
「日本経営研究所」は、
M&Aの総合支援を行う企業です
「プラットフォーム」✕「仲介」の
2つのサービスで、
あなたに最適なM&Aが見つかります
-
1.国内最大級の提携事業者数
-
2.安心の成功報酬型の料金設定
売り手様も買い手様も目的に沿った支援を行います
M&Aをお考えの方は、
どうぞお気軽にお問い合わせください【秘密厳守】